
掲載情報は2015年8月現在
| 所属 | 大学院情報理工学研究科 先進理工学専攻 |
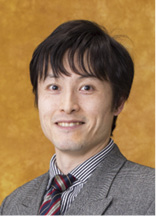
Masumi TAKI |
| メンバー | 瀧 真清 准教授 | |
| 所属学会 | 日本化学会、アメリカ化学会、有機合成化学協会、日本ペプチド学会、日本分子生物学会、日本蛋白質科学会、日本ケミカルバイオロジー学会 | |
| 印刷用PDF |
化学生物学、有機化学、光物理化学、癌細胞、蛋白質、ペプチド、人工アミノ酸、バクテリオファージウイルス、PET、陽電子放射断層撮影、NEXT-A反応
日本人の死亡原因の約3割が癌だと言われ、その割合は年々増加の一途をたどっている。そのため、体内に巣食う癌細胞をいち早く見つけ出し、効果的に駆除することが、医療業界の大きな課題となっている。しかし、別の場所に転移した癌細胞や、細かい場所に隠れているものまではなかなか見つけられない。また、癌細胞以外の正常な生体細胞にダメージを与え、被験者の体に副作用をもたらす場合も多い。最近では、副作用が少なく高効率で癌細胞を消滅させる抗体型の抗癌剤も登場しているが、大きな分子構造をしているために個々の癌細胞には届きにくく、効果が出ないといった問題も生じている。
当研究室では、有機合成化学と生物学をミックスし、それを物理化学が支えていく「化学生物学」をコンセプトにして、生物が生み出す抗体をヒントに、化学的手法を加えて新しい機能を持たせ、さまざまな分野に効果的に応用していこうという姿勢で研究している。具体的には、生体が作り出した抗体よりも小さいサイズの分子にすることで隠れた癌細胞も発見できる診断薬や、正常な細胞には一切悪影響を与えずに癌細胞だけを駆除する医薬品の研究開発を行っている。
癌細胞を効果的に見つけ出す戦略として、癌細胞にのみ結合する蛋白質やペプチドの末端に一定時間だけ陽電子を放出する人工のアミノ酸を導入させる。体内に入ったこの蛋白質やペプチドは、いち早く癌細胞を見つけだして結合する。その際にPET(ポジトロンエミッショントモグラフィー:陽電子放射断層撮影)を使って陽電子を検出することで、癌細胞の居場所を手早く特定することができる。この方法であれば、X線で見つけられなかった細かい癌細胞も確実に捉えることが可能だ。(JST研究成果展開事業)
癌細胞にのみ効く抗体代替品作りの戦略は、癌細胞にのみ結合する人工ペプチドをまず探索し、次にその末端に、白血球を誘引する抗体由来分子を導入する。この人工抗体代替品を体内に入れた際に、素早く癌細胞と結合させることを目標とする。その際、抗体由来の部分が白血球を誘引し、その白血球が人工抗体と結合した癌細胞を丸ごと“食べて”しまうことを期待している。
生体適合性のよい蛋白質をベースにした医薬品であるので、健全な細胞にはほとんど悪影響を与えずに、癌細胞のみを消滅させることが可能となるのだ。(NEDO先導的産業技術創出事業)

このように画期的な人工蛋白質を生み出すには、瀧が開発した「NEXT-A反応」が不可欠だ。これは、蛋白質やペプチドなどの生体分子の中の1カ所だけに人工物を結合させるための手法だ。具体的には、試験官の中にL/F-転移酵素、tRNA(転移リボ核酸)、アミノアシルtRNA合成酵素の3種類の生体触媒を混ぜておいて、蛋白質と人工アミノ酸を加えることで、人工アミノ酸導入蛋白質を作ることができる。きわめてシンプルな手法であり、加熱を一切せずにただ混ぜるだけで短時間で進行する反応であることがアドバンテージだ。
さらに、バクテリオファージウィルスを使えば、一度に1億個の薬剤の候補を簡単に作り出すことができる。このような1億個の人工分子を人間の手で合成しようと思ったら、膨大な年月がかかってしまうが、ウィルスの作り出す物質(蛋白質やペプチド)は必ず遺伝子と1対1で対応するといった生物の多様性を利用して、簡単に行うことができるのが大きなメリットだ(10BASEd-T法)。これとNEXT-A反応とを組み合わせて、新しい薬剤候補を作る。
さらに、瀧は化学に精通していることから、有機化学的に物質を設計できるという強みを持っている。つまり、単にウィルスが作り出す蛋白質を利用するだけでなく、より癌に結合しやすい分子を融合できることが大きなアドバンテージだと言える。

このNEXT-A反応や10BASEd-T法は幅広い分野に応用可能だ。このNEXT-A反応を使えば、蛋白質を生体外の電子材料や人工物に結合させることができ、医療分野以外でも広範にこの手法を活用できる。NEXT-A反応を行う上で副次的に合成した蛍光性アミノ酸はJSTシーズ発掘試験で研究を行い、現在は渡辺化学工業で製品化され、蛍光ペプチド合成用試薬として販売されている。
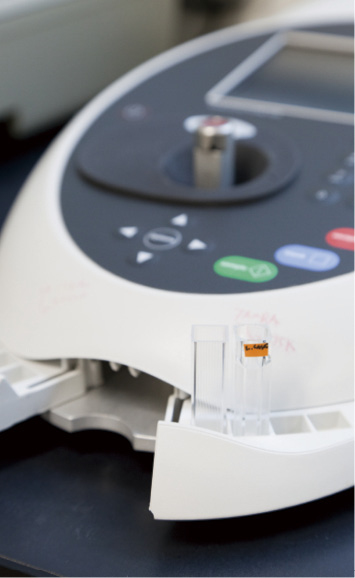
生物だけでも限界があり、これに化学の良いところを人間の英知で組み合わせることで、ほんとうに使える物が作れるのではないかと思っている。つまり、いかにしてうまい結合を作るかというところに化学の真髄があり、そこから新しいものを生み出していきたいと思っている。
瀧は、2011年、本学に着任したばかりではあるが、電通大らしい研究を行いたいと思っている。生体内での情報伝達ネットワークや情報コミュニケーションを何がどう司(つかさど)るかを解明したり、瀧の化学生物学的な知見を、電気・電子材料にも応用していきたい。最終的には「電通大だからできたバイオだ」と言われるものを生み出してみたい。


